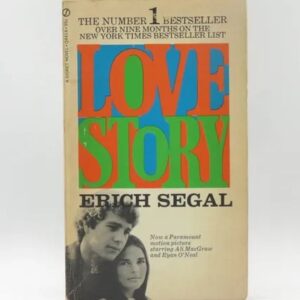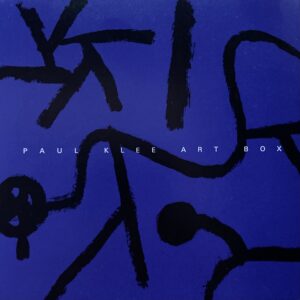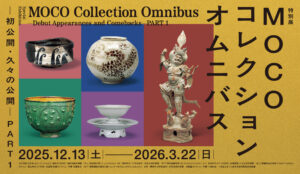約15年前のこと。当社のスタッフだったアメリカ人アルフレッド・ハフトの名をインターネットで見つけた。世界を視野に入れれば同姓同名の男性はいくらでもいるはず。しかし、さほど時間を要さずに、彼が大英博物館の日本担当学芸員であることを突き止めた。当社に勤務していたのは30年近く前だが、写真を見てすぐにわかったのである。
彼の著書に“Aesthetic Strategies of the Floating World”(「浮世の美的戦略」)という本がある。その副題が“Mitate, Yatsushi, and Fūryū in Early Modern Japanese Popular Culture”。研究テーマが「見立て、やつし、風流」だと知って彼らしいと思った。当社を離れてから、学者を目指して見立てを研究していたことに驚いた。
見立てとは判断や鑑定の意である。「そのネクタイ、センスがいいですね。ご自分で買われたのですか?」「いえいえ、妻の見立てですよ」というふうに使う。医者の見立てと言えば診断のことになる。
見立ては多義語で、「なぞらえる、仮定する、見なす」という意味もある。白洲に岩を置いて島に見立てれば風流な趣の庭になる。一見無関係な2つの対象を並置すると、機知に富んだ新しい意味が生まれやすい。射撃訓練で実際の人を撃つわけにはいかない。そこで、立ち木を人に見立てるのである。
見立ての身近な例に盆景がある。凝り性の父は正月が近づいてくると盆の上に土、砂、石、苔、小さな盆栽を使って、風景や山水、庭園を写実的に縮小して創作していた。「Aを無関係なBになぞらえる」のは西洋のアナロジー(類比)に似ている。観察眼と遊び心に裏打ちされてこその見立てである。