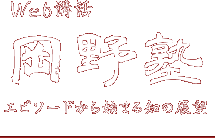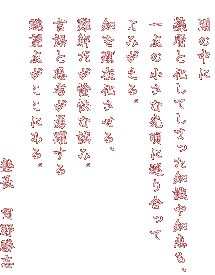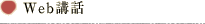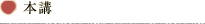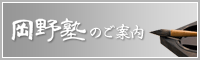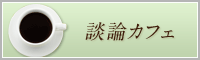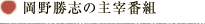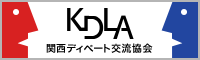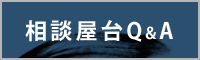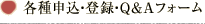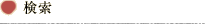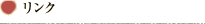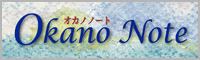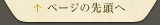第1講 マジカルコミュニケーションの03 「リーディング」
コンセプトに続いては「リーディング」を取り上げます。
リーディング、ふつうは「読書」という意味です。ここでも本を読むという前提で話を進めますが、必ずしも読書に限定しているわけでもないのです。どちらかと言うと、「読み取る、汲む、解釈する、見抜く」などのように、対象を書物だけではなく、広くメッセージや状況・場面を読むという意味で使います。そのほうが、コミュニケーションにふさわしいと思うからです。
ラテン語の"legere"には「読む」という系譜もあるけれども、書物が少なく希少だった時代に一般庶民が読書に親しんだはずがありません。だから主たる意味は、人の話を集める、摘み取る、収める、受ける、つかむなどのほうだったと思われます。文字を目で追う作業というよりも、見聞きする話や光景を刈り取っているという感じです。
▼ 読むとは「文脈」に入り込む作業
田畑に入って稲や小麦を刈るようなものです。森林に入って木の実を採るようなもの、河川で魚介を捕るようなもの。とにかく、その状況に入り込まねば何一つ手に入りません。次の文章を読んでみてください。
この場に及んで、まだ「そこのところを何とか」と彼は言う。 「きみ、まだそんなことを・・・・・・」 あとは言葉にならず、絶句してしまった。
ふ~ん、で終わってはいけません。お節介に文脈に分け入って「・・・・・・」の部分を読み、状況における関係性を想像してみる。なぜ絶句してしまったのか。もし絶句していなければ、どんなことばで後を継いだのか。行を足して行間を、文脈を読まねばならないのです。
▼ ことばのあやの技術「レトリック」を学ぶ
レトリックとは「修辞法、修辞学、美辞麗句、巧言」のことです。意味のレトリックや型のレトリックなどがあります。「鍋が煮える」や「電話をとる」というのは意味のレトリックです。実際に煮えるのは「具材」だし、実際にとるのは「受話器」です。それでも、具材や受話器を省略しても意味が通じます。
「だから言っただろ、気をつけろって!」というのは型のレトリックです。「食べましたよ、旬のホタルイカ」も同じ。本来の文章の型が倒置していますね。レトリックや比喩を読みこなすというのは、類推することにほかならないのです。
▼ 主題探し、主題文探し
話し手や書き手の言いたいことを汲み取ってみましょう。どんなことばの達人と言えども、コンセプトを100%表現できていることなどありえないのです。
その人の「一番伝えたいことは何か」を探り、そのメッセージがどの表現に結実しているのかを見て取る。これこそが、人間心理を読むマジックなのです。
▼ 要約、つまり「コンパクトに読み換える」
1000字の文章を100字に凝縮してみます。エッセンスを絞るのであって、抽象的にまとめるのではありません。ほんとうに重要なことは、いっさい手を加えずにそのまま抜き出す。こんなことをしていると、あっという間に50字くらいになってしまいますが、それだからこそ、必死に行数を絞り込もうとする工夫を凝らすようになります。
要約するとは、「抽出」であり、場合によっては「濃縮」であり、余分なものを切り捨てるという「削除」「放棄」でもあるのです。
▼ ウイットを読み、ことば遊びを楽しむ
「オレは記憶力が悪いと思い込んでいたが、まんざらでもないことがわかった。だって、さっき昨日が家内の誕生日だと思い出したのだから」。これはぼくのお気に入りのネタです。別に笑わせる表現を使っているのではないけれども、構成・展開の妙で論理が崩れるおもしろさがあります。今のは阿刀田高の本に書いてあります。ついでに、もう一つ、同じ本から紹介します。
「私には好きな女性のタイプは二つしかない。
このAとBにどんなことばを入れたらウイットになるか。「日本人と外国人」。これですべての女性が好きということになり、二つのタイプに絞った意味がなくなります。
平凡だと魔法の出番がない。魔法には「落差」が必要なのです。常識と非常識の落差、表と裏の落差、予期したことと予期しないことの落差。コミュニケーションが情報の共有化であるからこそ、逆に知っていることを再確認するだけでは物足りないし感動も薄い。一度落差感覚を挟むほうが感動も増幅されます。
▼ リーダーシップ・ボキャブラリー
リーダーなら自然流のことばの使い手で止まっていてはいけません。「何をどのように伝えるか」に関しては、つねに意識的であろうと努めるべきです。それによって、部下や顧客と一線を画する「リーダーらしき語彙の体系」が身につきます。
あなたは、良書に巡り合うために苦労していますか? 苦労して本を探し、苦労して読まないと、読書による知識習得、批判的思考、ボキャブラリーはなかなか身につきません。
なお、読書をすればするほど、知識が増えそうですが、実は、逆に無知を自覚するようになるのです。人間はどこまで行っても無知なんだなあ、ということに気づきます。読書のメリットは、「無知であることへの無知」を回避してくれることだとぼくは思っています。
▼ 「こなれた解釈」で文章を読む
名文を読むにこしたことはありません。しかし、手にした本がたとえいい内容であるとしても、名文かどうかはわかりません。人それぞれです。一般的な名文とは、美辞麗句で飾られたものだけとはかぎらず、平易でリズムがあり、ビンビンと語感を刺激してくれる文章です。
これぞという箴言や名言に目をつけて、よく熟読解釈して薀蓄を傾けてみることをお薦めします。実は、こういう習慣がマジカルリーディングの鍛錬につながるのです。最後に例題を出しておきますので、自分なりに読み解き一考してみてください。
1.人生は大写しにすれば悲劇だが、遠写しにすれば喜劇である。
2.かつて自分が存在しない時があったことなど、誰も気にしない。とすれば、自分がいなくなる時が来ても、何でもないはずだ。
3.人が本当に所有するのは記憶だけである。記憶の中でのみ、人は金持ちであり、貧乏である。
4.時計が止まる時、時間は生き返る。
5.楽観主義者はドーナツを見、悲観主義者はドーナツの穴を見る。
《04に続く》