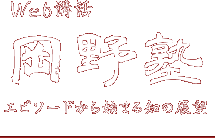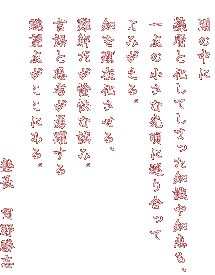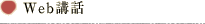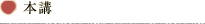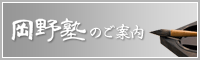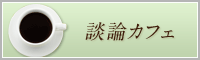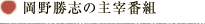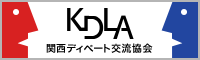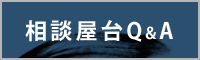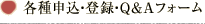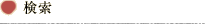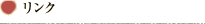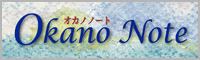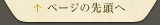第1講 マジカルコミュニケーションの04 「リスニング」
リスニングと言うと、ヒアリングと併せて外国語の学習と結びつくことが多いようです。使い慣れている母語の場合には、あまりリスニングやヒアリングなどと言いません。むしろ、「日本語なんて生まれ育った国のことばだ、聴く努力なんてしなくていいじゃないか」などと少々横柄な態度を取りがちです。
しかし、外国語になったとたんに、聴くことを異様にクローズアップします。それもそのはず、英語でもフランス語でも中国語でも、慣れ親しんだ日本語のように左団扇で聴き取れないからです。
でも、実を言うと、日本語だって十分に聴き取ってなどいないのです。物理的に聞き取れることと、意味されていることを認識できることは別問題なのです。
▼ 相手の話を理解しようと努めよ
たいていの人間は、関心事にしか耳を開きません。ぼくにもその傾向があります。「耳の痛いこと」や「興味のないこと」には耳のシャッターを降ろしてしまうのですね。ぼくたちは「壁に耳あり、障子に目あり」と言いますが、ユダヤ世界には「壁に耳あり、耳に壁あり」という諺があります。何と「耳に壁あり」です。意識的か無意識的か、たぶんその両方でしょうが、ぼくたちは壁を作って興味のない話や都合の悪い話をシャットアウトしているのです。
聴くとは、音声の聞き取りのみならず、意味の聴取のことでもあります。だから、つねに「傾聴」と呼ぶにふさわしいのです。理解しようという努力の前提に、批判的に聴くということがあってもいいでしょう。批判的傾聴力、「クリティカルリスニング(critical listening)」です。真偽を確かめたり因果関係を探ったりしながら聴けば、集中力は一気に高まってきます。
▼ 知識データベースと思考受容器を大きくする
当たり前のことですが、大きくてきめ細かい目の網のほうが獲物を容易に捕えることができます。情報についても同じです。知識や語彙力や思考力が粗っぽくて幼ければ、関心のある好みの情報しか入ってきません。
傾聴力の源泉に雑学、異種情報間の連想、思考材料の多さがあります。大きなアンテナを立ち上げましょう。そして、それでもなお不十分なのが現実です。その足りない部分を補うのが、たくましい想像力ということになります。
▼ 全身これ耳にして聴く
"I'm all ears."という英語の慣用句があります。直訳すると「私はすべて耳」「全身これ耳」ということになります。昔、たしかロマン演歌に「♪あなたの声に体じゅう耳になりそう」というのがありましたが、身の引き締まるような傾聴ぶりを表現していると言えるでしょう。
「先日、あるパーティーに出席したとき、おもしろい体験をしましてね・・・・・・」に対して、「ほう、興味津々です」というときに使う表現が"I'm all ears."です。「好奇心いっぱい」と言っているのです。
▼ 「聴くコミュニケーション」は人間関係の基盤
事業内容や企業の規模にかかわらず、組織はコミュニケーションを基幹システムとして動いています。コミュニケーションというレールがあるから、ビジネスが成立している。レールの上を走らない仕事は脱線してしまいます。
人と人の関係は、上司―部下、企業―顧客、先生―生徒、夫―妻など多種多様です。いずれにせよ、スムーズな関係づくりをコミュニケーションが支えています。そして、あなたが上位者でありプロフェッショナル度が相手より高い、また、あなたには譲歩できる力量があり、しかもリーダーシップを発揮したいという自覚があるならば、ひとまず「聴くコミュニケーター」を演じるべきでしょう。ぼくも反省しなければなりませんが、リーダーや経営者は無意味でムダなお喋りが過ぎて、人の話をあまり聞かないのです。
▼ 音声は消える、ゆえに聞き逃しの油断禁物
日本社会では目と目を向き合わせて会話や対話をすることはめったにありません。相手の目を凝視すると変な人に思われるかもしれない。そこで、なんとなく視線をそらしてしまう。
欧米人は相手の目を凝視します。シャイな人もいますが、会話になると目を逸(そ)らさずに相手の発言に聞き入ります。油断していると「打てば響くような会話」ができないからです。男性名詞・女性名詞、単数・複数など変化に富み、なおかつ時制変化が複雑な言語においては、受け答えの代名詞も勝手に使えません。まさに、コミュニケーションが真剣勝負そのものなのです。
▼ ことばを聴くのではなく、コンセプトを聴く
「観音」ということばが不思議だと思いませんか。「音を観る」のですよ。音声というデジタル信号をデジタル処理するのではなく、イメージに転換(アナログ化)して観るのですから、すごいことです。
音声は毎秒10ビットしか処理できません。これに対して、画像には毎秒100万ビットの情報を伝えうるだけの圧縮機能があります。結局、人間の言語活動というのは、観察したこと(つまり、アナログ情報)の言語化(つまり、デジタル化)であり、言語というデジタル記号を通じてのアナログ現象の理解という、《デジタル⇔アナログ変換作業》にほかならないのです。
▼ 聴くとは「アタマの中で心象メモをとる」こと
飲み込みが早い、理解力にすぐれているとはどういうことでしょうか。よく見れば、メモを取っているわけでもないのに、要所で的確にまとめたりタイミングよく話題に乗っかってきたりできる人がいます。逆に、ホワイトボードの文字をすべて丸写しし、うんうんとうなずいていても、まったく何も聞き取れていない脳細胞の持ち主もいます。あなたはどちらですか?