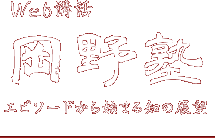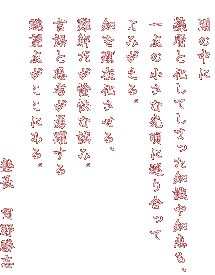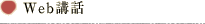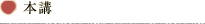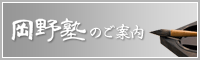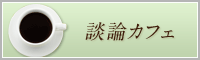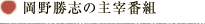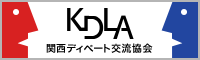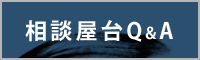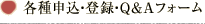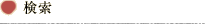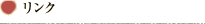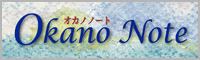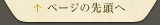ロジカルトークのすすめ
両極からグレーゾーンが見える
「体調不良かも」と自己判断できるためには、これに先立って「体調良好」が体験されている、あるいはその概念が認識できている必要があります。ある理想なり解決状況がイメージされていなければ、問題を問題として特定することはできません。異常は正常感覚によって、混沌は秩序感覚によって察知されます。
論理思考のツール(2)
演繹的推論
推論とは、一つまたは複数の前提から結論を導くことです。「AならばBである。AでありBであるならばCである」という具合。ある前提を認めると、そこから導出されることも確実になり、結論も認めることになります。演繹的推論は実際の事実を踏まえて展開するものではなく、前提の積み重ねによって結論を論理的かつ必然的に導いていくのです。
論理思考のツール(1)
主張とは何か
英語に"claim"という語がありますが、これはぼくたちがよく使う「クレーム」とは意味が異なります。和製のクレームは「文句」という意味合いが強く、英語では"complaint"になります。英語の"claim"は要求などの主張を意味します。
どんな主張も「意見の誇示」です。なぜ誇示するのかと言えば、納得、共感、共有、同意などを対象に期待するからです。ぼくたちはどうでもいいことを主張したりしません。主張するかぎり、その主張を通したいのは当たり前です。
論理思考の基本(2)
論理は大より小、広さより狭さ、総論より各論、抽象より具象を求める
たとえば、文脈上「京都」と言えるとき、わざわざ「日本」という大きな概念を持ち出すべきではありません。固有名詞がわかっているのなら、漠然とした「犬」という表現よりも「ヨークシャーテリア」と言うほうがいいのです。「そこに道具があった」ではなく「ノコギリが置いてあった」、「その女性」よりも「二十代前半のその女性」のほうが、相手には伝わりやすいのです。文学的効果を狙うのでないかぎり、概念を絞って単刀直入に表現するのが論理思考には不可欠です。
論理思考の基本(1)
論理的であるということ
「あなたは論理的ですね」と言えば、段階を踏んで話したり書いたりしている、あるいは筋が通っているという意味になります。しかし、同時に、「ことばに敏感ですね」という、暗黙の意味も込められています。ことばをいい加減に使う人、語感や表現差異に鈍感な人が論理的になることはありえません。論理(Logic)とことば(Language)は同源なのです。
ロジカルマインド
ロジックは伝家の宝刀
どんな場合でもロジックの刀を抜いてはいけません。安っぽい竹光みたいになってします。論理の使い手だと勝手に思い込んでしまう人がいますが、たちが悪く人を困らせます。気をつけましょう。論理には出番や適所というものがあるのです。
原理原則を共有している組織・集団において、仕事やプロジェクトに論理を「標準語」として使うのは問題ありません。しかし、原理原則すら共有できていない二者間の交渉・折衝などでは、論理以外の力学が作用します。
プロローグ
ロジック(論理)についてぼくなりの見解を示すことはできますが、それが明快であり安定していると言える自信はありません。ずいぶん長く「論理的な話し方」だとか「論理的な文章」などの言い方を平気でしてきましたが、さらっと使っているわりには、意味がぼくの中に十分に浸透しているようには思えないのです。考察するたびに「論理とは何か」への答えが少しずつ変化します。
ふつうに考えれば、思考に筋道をつけ、思考力を効果的にしてくれるものが論理なのでしょう。話すこと、書くことは間違いなく論理に関係があります。しかし、論理的(ロジカル)であることが理屈っぽいなどと受け取られることもよくあります。目的や状況次第では、たしかにロジカルであることが無意味であったり場違いであったり屁理屈になったりすることは否定できません。
エッセイの基本(その3)
『スピーチとエッセイの技法』もいよいよ今日が最後。言い残したことを振り返ってアトランダムに話すことにしましょう。
11 分解・分類
テーマ(主題)は小さければ小さいほど書きやすくなります。思い切って絞り込みましょう。どうしても大きいテーマを扱わねばならないときは、いくつかのキーワードに因数分解してみることです。総論、抽象概念、大言壮語は理解の敵です。一般的に部分は全体よりつねにわかりやすいのです。
エッセイの基本(その2)
エッセイストでもないのに書いてもしかたがないと思っている人がいます。文章を書くのは、必ずしも誰かに読んでもらうためや発表するためではありません。書くことは思考を明快にしてくれるのです。
古代ギリシアでは文字にすることを蔑んで、語ることばを上位に置いた時代がありました。それでもなお、思考を形にするうえで書くことに依存したのです。では、前回の続き。エッセイのヒントをさらに6ヵ条。
エッセイの基本(その1)
前回までスピーチの話をしてきました。今日からはエッセイです。スピーチのコツやヒントのほとんどは書くことにも当てはまります。但し、何について、誰に対して、どんなトーンで書くかという点に関して、エッセイのバリエーションはスピーチを凌ぐでしょう。書くことを負担に思う人も多いですが、臨機応変というスピーチならではの手かせ足かせを外せます。
とらわれのないスタイルで思いや意見を述べたり読み手を楽しませたりなど、スピーチに比べれば自由奔放に振る舞うことができます。生放送のスピーチでは「かくあらねばならない」という意識が強くなりますが、エッセイではそのような強迫観念は無用です。しかし、メッセージをよく伝えるためにはエッセイ固有のコツと法則もあります。